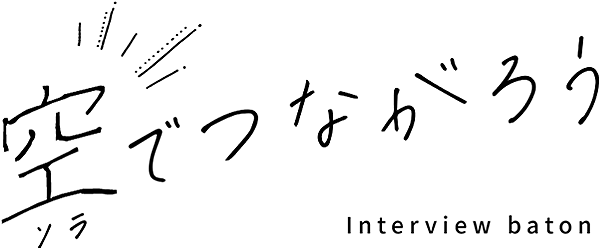
Interview Vol.114
ミューラル(壁画)を日本に広めて、
アートをもっと身近な存在にし、
街と子どもたちの未来を明るくする。
長谷工グループのインキュベーション組織「UXDセンター」が行う共創プロジェクト「EVOLOVE(エボラブ)」は、2025年、日本各地の“街を明るくする”活動を開始します。
あなたにとって“明るい街”とはどんな街でしょうか?商店街に活気がある街、街灯が増え夜も安心な街、若い世代が移住してくる街、大学を卒業したら子どもたちがまた戻ってくる街、多くの観光客が遊びに来る街、季節ごとに花が咲き乱れる街。あなたの街をもっと“明るい街”に変えるために、みなさんはどんな活動をしているのでしょうか。
今回は、各街でミューラル(壁画)を描くことを通して、街を明るくする活動を行うWALL SHARE株式会社の川添孝信さんに話を伺いました。
街のためだけではなく、
アーティストがよい作品を残せること。
それが結果として街を楽しくする。
現在の活動について教えてください。
川添ミューラル(壁画)を主軸とする、日本では珍しい活動を行うWALL SHARE株式会社を経営しています。世界のアーティストとコミュニケーションを取りながら、キュレーションを行い、ミューラルをプロデュースしています。ミューラルを軸として、企業のプロモーションを行うこともあれば、まちの活性化という面から行政とコラボレーションという形でプロジェクトを行うこともあります。こうした活動を通してミューラルを増やす取り組みを行っています。

WALL SHARE株式会社・代表取締役の川添孝信さん
「街をあかるくする活動」について、取り組みのきっかけを教えてください。
川添僕は10代からずっとラップを聴いていて、同じカルチャーにストリートアートが存在していてその頃からずっと好きでしたね。起業するまでは現在とは異なるキャリアを経ており、アート界の出身でもなかったのですが、ミューラルというカルチャーを日本でも広めることができればおもしろいと考え、ワクワクした気持ちでスタートしました。
どのような思いで「街をあかるくする活動」を行っているのでしょうか。
川添世界のアート市場は約9兆円といわれていますが、日本では3%未満にとどまっており、まだまだアートは身近ではないと感じています。美術館へ行ったり、絵を買ったりする機会は減っていますが、それでも僕はアートはもっと日常に必要だと思っています。街にミューラルがあれば、アートに触れる人々の数をどんどん増やすことができるという思いがあります。無表情の壁がアートで彩られることによって、多くの人が見に来てくれるかもしれないし、足を止めてくれるかもしれないし、描いているアーティストに話しかけるかもしれない。そんな機会を増やしたいと思っています。

「MURAL TOWN KONOHANA」Bernhardさんの作品(大阪府此花区)

「MURAL TOWN KONOHANA」Forkさんの作品(大阪府此花区)

「MURAL TOWN KONOHANA」Dan Kitchenerさんが製作中の様子(大阪府此花区)

「MURAL TOWN KONOHANA」Jacklackさんが製作中の様子(大阪府此花区)
「街をあかるくする活動」の事例を教えてください。
川添コロナ禍の渋谷で、飲食店の支援につながる可能性があるのではと飲料メーカーとコラボし、シャッターアートを展開しました。オーナーさんからは、足を止めて見てくれる人がいたという声が届きました。
2023年から大阪・此花区で、富士フイルム株式会社と進めている国際的なミューラルプロジェクト「MURAL TOWN KONOHANA(ミューラルタウンコノハナ)」は、世界中のアーティスト達(現在16か国)が、自分の作品を日本ならどう描くだろうということで共通のテーマもなく描いています。また2025年4月には、北九州市の門司港で、北九州市が進める「新居浜倉庫群アートプロジェクト」で、倉庫の壁面にアートを描く取り組みに参画しました。ここでミューラルキッズプロジェクトとして行った、子どもたちが壁画を描くワークショップでは、約40名の子どもたちが集まりました。

「新居浜倉庫群アートプロジェクト」でのキッズミューラルワークショップの様子(福岡県北九州市)

「新居浜倉庫群アートプロジェクト」でのキッズミューラルワークショップの様子(福岡県北九州市)
また沖縄市コザでは、地元の人も絡めたミューラルフェスを展開していますし、大阪府茨木市では新築のマンションの仮囲いに、地元の大学生の提案を生かしたアートを描くプロジェクトも行いました。このように、今はありとあらゆるエリアで、ミューラルを生かした活動に取り組み始めています。
僕たちは、「この壁に対してこういう作品を描いたら、この街にとってはいいかもしれない」という思いでキュレーションをしています。街のためというだけではなく、アーティストがよりよい作品を残せることが、結果として街を訪れた人が、アートを通して街をより楽しめることに結びつくと思っているので、アーティストのテイストやバランスは慎重に考えて選考しています。
川添さんにとっての地域活性を教えてください。
川添海外ではミューラルによる街の活性化事例がたくさんあります。治安の悪い地域や繁華街ではない地域にミューラルが増えた結果、観光地化されたケースも見られます。日本ではまだ少ない事例ですが、大阪府此花区も一つの活性化事例になりつつあると感じています。

ミューラル制作中に通りすがる人たち(大阪府此花区)

完成したミューラルを眺める通行人たち(大阪府此花区)
人が手描きで大きなものを描くということは、人の心を動かすものであると思っていますし、実際に街の壁画を見るためにわざわざ遠方から足を運ぶ人もいて、その街の飲食店で食事をして帰る、という人も増えてきています。こうした循環ができていることはいいと感じていますし、深めていきたいとも思っています。また、一回描いただけではなく、継続性をもたせることができるのであれば、さまざまなエリアで展開する意義はあるように思います。継続性を前提とした仕組みが作れるのであればより街の活性化につながっていくと考えています。
子どもたちがもっとアートに触れて
将来「アートってカッコいい」と思える、
そんな日本にしていきたい。
川添さんにとっての“EVOLUTION✕LOVE”を教えてください。
川添日本にとってアートがもっと身近になるといいな、という思いが根底にあります。しかし今すぐに状況が変わるのかといえばそうではなく、時間がかかることだと思っています。そのためにみんながアートに触れられるきっかけをなるべく作りたいと考えているのですが、特に子どもたちにフォーカスを当てています。子どもたちにとってアートが身近に触れられる街になること。海外ではそういう場所が多く見られますが、例えば日本でも、小学校1年から中学3年まで通う通学路に、同じミューラルを見続けるという子どもたちも増えれば、「子どもの頃学校に通った道に、すごく巨大なアートがたくさんあった」とか、そういう記憶や経験はずっと残ると思うんです。その子どもたちが大人になった時に日本のアート業界が少し変わる、そんな世界にすることが僕のEVOLUTION×LOVEだと考えています。
子ども向けのワークショップでも、子どもたちが無邪気に絵を楽しんで描いている姿を見ると、「大人はかっこつけてるな」とハッとさせられます。人が見ているとか、そんなことに合わせなくていいんだという、素直な感性を持ち続けられたらいいですね。

「HANASAKA MURAL」でのキッズミューラルワークショップの様子(大阪市東住吉区)
10年、20年後はどうなっていたいですか?
川添僕たちはこれからもずっと壁画を増やし続けようと考えているので、10年後どうなっているかというよりも、この考えを変えずに規模を大きくして増やし続けていきたいと思っています。また日本のアーティストがもっと海外で描けるチャンスや、海外のアーティストが日本で描ける機会を、もっと橋渡しできたらいいとも思います。その結果、ミューラルというカルチャーを、「いいよね」と思ってくれる人が増えるかもしれませんし、活躍するアーティストも増えるかもしれません。子どもたちが「アートってカッコいいよね」と感じてくれる世の中に、少しでも貢献できていたらいいなと思っています。

川添さん、ありがとうございました!ミューラルを通じて街を明るくするだけではなく、日本や世界のアーティストたちが活躍できる場をもっと増やそう、子どもたちがアートに触れる日常を増やそうと活動される川添さんを、今後も応援させていただきます。