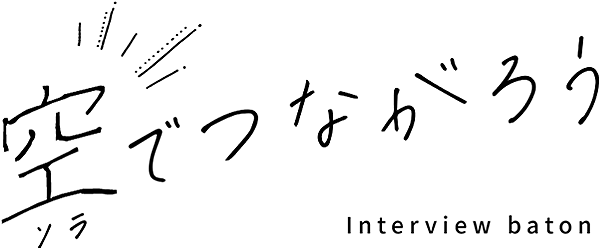
Interview Vol.131
東近江市で「ファブリカ村」の運営を通して、
滋賀のものづくりや豊かな暮らし、文化を発信。
EVOLOVEプロジェクトでは、日本全国47都道府県にて「地元愛」を持ち、積極的に地域活性に力を注ぐ方々へのインタビューを行っています。これまでの活動内容から、この後どのように「地元愛」を進化させていくか。未来へ向けたチャレンジを、皆さんと一緒に考えていけたらと思っています。第131弾の今回は、滋賀県東近江市で作り手と使い手、社会をつなぐ場所として「ファブリカ村」を運営する北川陽子さんに話を伺いました。

北川陽子さん
父が遺した工場を改装し、
みんながやりたいことをやれる
「つくるよろこび ファブリカ村」を創設。
現在の活動について教えて下さい。
北川東近江市で「ファブリカ村」を運営しています。地域ブランドである近江の麻や、地元の素材を使ったオリジナルの洋服やストール、アクセサリー、地域の作家たちが作る器や雑貨などをセレクトして販売しています。またものづくり体験をはじめ、地域の作り手たちのコミュニケーションの場としても展開しています。また湖東繊維工業協同組合や東近江市商工会に所属し、さまざまな活動をしています。

ファブリカ村外観
東近江市で活動することになったきっかけを教えてください。
北川65年前に父が北川織物工場を立ち上げ、家族で営んでいました。いわゆる昭和の時代に嫁入り道具として持たされた寝装寝具を作っていて、大阪や京都のメーカーの下請け仕事をしていて、私も高校生のときから繁忙期になると手伝っていました。大学は京都の美大に進学しましたがそのまま家業に入りました。
ところが時代の変遷とともに生活様式も変わり、婚礼需要がなくなってきたことと、エアコンの普及により季節の布団や座布団なども必要がなくなってきて。うちは夏の寝装寝具を中心に生地を作っていましたが、うちをはじめ地場産業がどんどん衰退してきたので、湖東繊維工業協同組合として「今までのような下請けの産地から提案型の産地になっていこう」という動きが始まりました。デザインの指導者が来て、各社の社長や代表たちが色やデザイン、トレンドについて学んだり。その結果、寝装寝具や反物から始まったこのエリアは、洋服地やインテリアの素材を手がけるなど大きな変革を遂げ、今では20社ぐらいがそれぞれの特徴を持ったビジネスを展開しています。
そんな中、うちは家族経営の小さな工場だったので、価格では到底勝負ができないから、父が持っていたかすりの技術を応用したものを作り、販売をしていました。でも父が亡くなって「さあ、どうする」となって。ちょうど私はその頃、クラフト展などでさまざまな思考を持った人と出会い、自分自身もこれまでのビジネス思考から、ものを作るということ、それを伝えるということを体感していて、これからは単にものを作って販売するのではなく、「誰がどこでどんな思いで作ったのか」というストーリー性を持たせることが大切だと考えていました。私たちが手間ひまかけて織ったものも、ちょっとした傷でB級扱いになり、焼却されてしまう。そんなのでいいのかってね。だから作り手たちの思いをお客さんに直接伝えて商品を買ってもらう場を作りたいと、自社の工場に「ファブリカ村」を立ち上げました。消費者が正しい選択肢を持てるような場所にしたいという思いですね。うちはノコギリ屋根の木造工場ですが、それまで使っていた機械を全部出して、「これからは織物をするのではなく、人を繋いだり、何かをしたいと思っている人がやりたい時にやれる場所を提供していこう」と考えて、豊かな暮らしという大きなテーマの中で「つくるよろこびファブリカ村」というキャッチフレーズをつけて開設しました。
「ファブリカ村」を作る気持ちを後押ししたのはクラフト展での作家さんたちとの出会いもそうですが、なんといっても場所があったことが大きいと思っています。父が遺してくれた場所を最大限に活かしたいという方法を、私なりに考えて出した結果が「ファブリカ村」の創設です。
実は「ファブリカ村」を作る10年くらい前から、工場内にギャラリーを作ったり、ストールの巻き方教室や浴衣パーティーなどのイベントを行ったりしていました。その経験を通して、人は楽しいことがあれば集まるし、伝えることができるというのは学んでいて。そこでたくさんの人との出会いがあったことも大きいですね。

「0歳からのジャズライブ」イベントの様子
北川さんにとっての地域活性を教えてください。
北川「ファブリカ村」を作って以降、この地域で空き家を活用した場所づくりがすごく増えました。「ファブリカ村」という拠点があれば、人が集まり、自然に情報が集まります。例えばママたちの居場所がないとか、不登校の子どもたちの問題とか、課題も見えてきて、その解決方法を考えることもできます。まちづくりに関わる人たちの視察も、取材も増えました。ファブリカ村をキッカケに、沢山の広がりが地域活性につながっていると思っています。私自身も東近江市商工会や観光協会から頼まれたら、やれることはなんでも受けるようにしています。そうやって活動をしていくと、私とはぜんぜん違う考え方の人の意見を聞くことができて、学びにつながります。
滋賀県は本当に住みやすい場所。滋賀県の人たちは琵琶湖の豊かな水や自然に触れて生きているからか、割とおおらかな人が多いような気がしますね。繊維関係のものづくりには水が重要なファクターですが、滋賀県にはこうした豊かな水がある。だから私は自分が生まれ、家業を営んできたこの町を大切に思っています。「ファブリカ村」も、ここに住む人たちが楽しく活動して暮らしていけるような場所にしたい。住んでいる人が楽しそうにしていたらみんな好きになってくれると思うので、「ファブリカ村」に来られた人たちが滋賀を好きになってくれるよう、おもてなしの心は常に大切にしています。「近江商人三方良し」の心は常に私たちの中に根づいていますね。それも地域活性につながると考えています。

ファブリカ村で行われたビジネスカフェイベント(2025年9月)
人間力と企画力を大切にしつつ、
与えられた役割を果たしていく。
北川さんにとっての“EVOLUTION✕LOVE”を教えてください。
北川私の原動力は「ファブリカ村」で何かをすることによって人が喜んでくれること。その姿を見ることが嬉しいし、そういう場づくりができていること自体を嬉しく感じます。私は、進化していくのは人しかいないと考えています。これから時代はますます便利になって、AIもさらに使われるようになっていきます。でもその時こそ大切なのは人と人との対話、人間力です。「ファブリカ村」には今、パン屋さんや花屋さん、お菓子屋さん、アトリエが入っていて、その方たちの家賃をもとにものづくりや何かをしたい人を応援しています。また私がこうした活動をすることによって、講演会や勉強会などにも関わることができ、東近江市観光協会でイベントのお手伝いをするきっかけも増えています。東近江市観光協会の例でいえば、8年前から地域の店やお寺で行うワークショップが始まっていて、最初は20ほどだったのですが、今は106プログラムにまでなりました。これらに陰ながら協力できていることが嬉しいし、こうした人間力や企画力を、地域の人々にも当たり前にしてほしいと思っています。
さまざまな場面で今の私に与えられた役割を果たすこと、それが私にとっての“EVOLUTION✕LOVE”です。

ファブリカ村15周年記念パーティー(2024年10月)

北川さん、ありがとうございました!「ファブリカ村」の運営や行政との関わりとの中で自分の役割を務めながら、滋賀の豊かな暮らしや文化を伝え、広げる北川さんの活動を、今後も応援させていただきます。