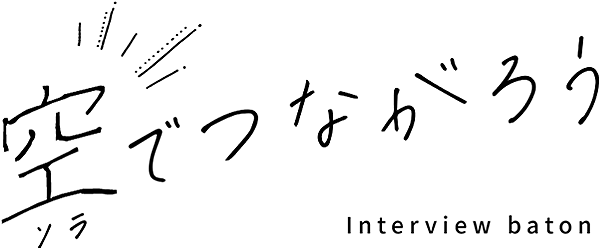
Interview Vol.67
宮崎から「ONE KYUSHU」思想で
九州全体をつなげ、未来をつくる
EVOLOVEプロジェクトでは、日本全国47都道府県にて「地元愛」を持ち、積極的に地域活性に力を注ぐ方々へのインタビューを行っています。これまでの活動内容から、この後どのように「地元愛」を進化させていくか。未来へ向けたチャレンジを、皆さんと一緒に考えていけたらと思っています。第67弾の今回は、九州全体の農業資源や技術、魅力をつなげて新たな食のプロダクトを生み出し、「地元創生」を展開する「一平ホールディングス」村岡浩司さんにお話を伺いました。

村岡浩司さん
地元の魅力で活性化させる
「地元創生」が重要
現在の活動について教えて下さい。
村岡大きく2つに分かれます。ひとつは食に関わる事業として、九州パンケーキミックスを中心とした加工食品の商品開発を行うプロダクト事業や、九州パンケーキカフェなどのレストラン事業を展開しています。代表的な商品が九州パンケーキですね。九州パンケーキは宮崎県綾町の無農薬の発芽玄米、長野県雲仙のもちきび、佐賀県の胚芽押し麦など九州の素材だけで作られていて、この粉を使って、九州チーズタルトやワッフルなど様々なスイーツを展開ています。
もうひとつは九州をひとつの島のように捉えて、この島の中にあるさまざまな農業資源や技術、人の魅力、伝統などをかけ合わせて新しいものができないか模索する活動を行っています。
県境や自治体単位にとらわれず、大きな枠組みでもとごとを捉えようという呼びかけをしていて、私たちは活動の理念を「ONE KYUSHU」という標語で表していますが、この言葉には「境界を溶かす」「越境する」というような意味が込められています。
国は約10年前に、人口減少問題を危惧して都市の一極集中から地方を活性化させる「地方創生」という政策を作りましたが、未だ課題解決の糸口は見えません。これからは、都会と地方という二軸対立ではなく、私は自分たちが住んでいる場所や土地の魅力を活かして地域主体で未来を作る「地元創生」が大切だと考えています。それで九州各地の多様な分野で活躍する人を呼んで「ONE KYUSHUサミット」を行ったり、「KYUSHU ISLANDプロジェクト」を立ち上げて、九州の未来について語り合ったり、賛同してくれる方々とともに九州の素材を使ったものづくりの支援を行ったりしています。
「ONE KYUSHU」への想いを教えてください。
村岡私が九州パンケーキを開発してから12年が経ち、「ONE KYUSHU」という言葉を掲げてから8年、「地元創生」を言い出してから6年が経ちます。自分の生まれ育ったまちで希望を持って暮らしていく、事業を営んでいくというのが地元創生の考え方です。しかし、一方で少子高齢化の課題は歯止めがかからず、消滅可能性都市とか限界集落のような強い言葉が、町の未来を信じる心を殺してしまっていると僕は思っています。そう言われるとみんなが絶望しますよね。
先日、西米良村に呼ばれて村長や町役場の方と話す機会がありました。西米良村は「1,000人が笑う村」という素敵なキャッチフレーズを作っていますが、コロナ禍で人口が1,000人を切っていて、商店もスーパーもなくてみんなが「この村で商売しても仕方ない」と言うんですよ。しかし、聞けば週に数回、隣町から魚屋さんやパン屋さんなどが外商に来て完売して帰っていく。小さいながらマーケットは存在しているのに、自ら商売をすることは悲観して諦めてしまっているんです。こうしたまちでも、1軒の小さな商店が開けば未来に希望の明かりが灯るかもしれない。豊かな営みは、他人から「消滅可能性」などとレッテルを貼られて諦めるのではなく、住民自らが作り上げていこうとする想いの先にあるのではないかと感じるのです。
また、九州という島のポテンシャルを再考することも大事かと思います。九州リージョンには1,400万人の人口規模があってそれだけでも大きな経済規模が存在していますから、県境というナワバリ意識を溶かして、大きなエリア感覚を持つことも重要です。海外へ目を向ければ、九州から東京の同じ移動距離で南に視点を変えれば台湾があるので、併せれば4,000万人のマーケットですよね。同じく西に行けば韓国があって、そう考えると近隣諸国をマーケットとして捉えればすぐに日本の人口規模を超える。
次の世代の人々はこうした九州の地の利を意識したビジネスを組み立てていかなければいけないと思っています。休日は車で1時間、2時間の移動はストレスが無いし、また、連休や祭日などは良い店には九州全体から来客がある。たとえ小さなレストランや個人事業であったとしても、商圏を自在にストレッチできるマーケット感を学んでいかないといけない。あと10年も経てば、きっとみんな“九州を一つの大きな島”と捉えて、長年縛られてきた県境の壁に囚われることなく自由な生き方をしている時代が来ると信じています。
いつか、“世界が憧れる九州をつくる”というのが私のライフタイムコンセプトなんです。
「KYUSHU ISLANDプロジェクト」とは?
村岡「KYUSHU ISLANDプロジェクト」とは、ものづくりをしている九州の事業者が新商品開発に挑み、クラウドファンディングMakuakeを活用してテストマーケティングを行うという共同体のことです。この3年で約90のプロジェクトが立ち上がり、200社くらいがコミュニティの中に存在します。プロジェクトに参加している事業者さんは九州中に点在しているので、産地情報や加工工場の技術なども共有化できます。九州という大きな単位の様々な情報を活用しながら、人と人を繋いでいくことで、新しい価値が次々に生まれ始めています。今後、新たな商品が更に増えていけば、共同での販路開拓やマーケティングができるのではないかと考えています。点で繋がって広がっていく、でっかい地域商社のようなものですね。

地元クリエイターと進める、空き家をリノベーションした拠点づくり
マイクロビジネスが持つ可能性が
町に人を惹きつける
村岡さんにとっての“EVOLUTION✕LOVE”を教えてください。
村岡私は1軒の古着屋から商売を始め、カフェやいろいろな事業を行って、時には拡大思考で成長を追いかけてきました。そんな折、2020年からのコロナ禍で多くのものを失い、経営者としての失望と自己否定の日々を過ごしてきました。時代は移り変わり、今では、昔から変わらない小さな商売「マイクロビジネス」の可能性を感じています。小さな町にとって、1軒のカフェや飲食店は未来を変える力があるということです。もちろんスタートアップはこの国の未来を作り、時には人類全体の進化にもつながる。でもそれができるのは数万人に一人です。地域には、いつの時代もその土地への思いを持った商人が必要だと思います。
当社は廃校を利活用していますが、その1階に「MUKASA Coffee&Roaster」という小さいカフェを作りました。1週間分のコーヒー豆を焼き、九州の小麦を使ったパンを焼いて、木・金・土・日5時間だけ営業していますが、週末は行列です。数万人しかいない町でもSNSを活用すれば誘客できる時代になりましたよね。
昭和後期から平成にかけては時代がひたすらに拡大路線の一途を辿っていました。大手のチェーン店がどんどんできて町の寿司店やケーキショップへ引導を渡していきました。しかし、令和は個性回帰の時代だと考えています。ユニークなアイデアを持ったこだわりの表現、そこに惹かれて、日本中、世界中の人が来る。私にとっては、マイクロビジネスが持つ可能性がEVOLUTION✕LOVEです。

地域に人気のムカサコーヒーの手作りパン
村岡さんがめざす九州の未来を教えてください。
村岡国際的な都市間競争がますます激化する中で、東京は日本の未来を背負い続ける宿命とともに、世界の中の巨大都市としてこれからも輝いていかなくてはならないでしょう。それは資本主義の戦いでもあり、弱いものが淘汰される弱肉強食の未来です。でも地方に住む私たちはそれに飲み込まれるわけにはいかない。自分たちで生き方を設計していくことがすごく大切だと考えています。
九州という国のこれからの成長戦略を捉えたとき、福岡はやっぱり中心的な役割を果たしていかなくてはならない。一都市だけが成長すれば良いわけではないという「ONE KYUSHU」の思想を持って、九州全体の成長と発展にどのように貢献できるかという矜持は、人口減少時代においては、ひいては福岡の都市戦略上も大切な考え方となるはずです。
限界集落とか消滅可能性という言葉に惑わされる中で、どこに希望が見いだせるかというと、やっぱりつながりです。「ONE KYUSHU」思想であらゆる壁を溶かし、ぜんたいの豊かさを設計していく、そんなつながりを基軸とした経済発展(Community based economy)はこれからますます進化して深くなっていくと思います。

ONE KYUSHUサミット当日の様子
今年、「ONE KYUSHUサミット」の実行委員長を20代の女性に委ねました。学生もたくさん参加してくれたし、彼女たちが「次のONE KYUSHUサミットはどうしよう」と自分の言葉で話している様子を見て、結果は大成功だったと感じています。私は、方針や場所も全部自分たちで決めていいよと話しています。規模も必ずしも大きくなくて、五島のような小さいところでやってもいい。規模にこだわらず、年齢にもこだわらず、若い人も高齢者も一緒にやってもいい。これまで社会の底に横たわってきた壁を溶かしていくのが僕らの未来です。それぞれが独立しながらも一つの目標に向かってつながっている、不思議な有機体のようなコミュニティを作ることができたことに対して、仲間にすごく感謝しています。これはもう多分、私がいなくても動いていく思想になったと思いますし、10年後にどのように進化しているのか、それが今からすごく楽しみです。

村岡さん、ありがとうございました!九州をそれぞれ県ではなくひとつの島として捉え、「ONE KYUSHU」で未来を作っていくという考えに、九州の限りない可能性を感じました。「ONE KYUSHU」の今後の活動と発展に、大いに期待しています!