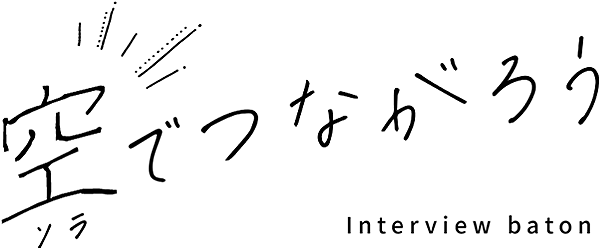
Interview Vol.90
琵琶湖版SDGsを運営し、
滋賀県内の行政や企業、地域を連携させて
琵琶湖の環境保全と地域活性化に尽力。
EVOLOVEプロジェクトでは、日本全国47都道府県にて「地元愛」を持ち、積極的に地域活性に力を注ぐ方々へのインタビューを行っています。これまでの活動内容から、この後どのように「地元愛」を進化させていくか。未来へ向けたチャレンジを、皆さんと一緒に考えていけたらと思っています。第90弾の今回は、琵琶湖の水質や環境保全のためにゴールを掲げて活動する琵琶湖版SDGs「マザーレイクゴールズ(Mother Lake Goals: MLGs)」案内人代表の佐藤祐一さんにお話を伺いました。

魚道づくりの際に参加者の皆さんと佐藤さん(左から2番目)
「マザーレイクゴールズ」を通して
行政と、若者や地域の人々がつながり
さまざまな活動を実現化。
現在の活動について教えて下さい。
佐藤滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究員として、琵琶湖の水質や生態系保全に関わる調査研究を行っています。また2021年から琵琶湖版のSDGs「マザーレイクゴールズ」を立ち上げ、琵琶湖を切り口に13の目標を独自に設定し、琵琶湖の環境だけではなく地域の多様な課題解決につながるような活動を行っています。
「マザーレイクゴールズ」には多くの人たちが関わっていますが、活動を広げるコアメンバーである「案内人」は現在20人ほどいて、私はその代表を務めています。その活動の一環で、例えば僕は子どもの環境学習を実施しており、地元の方々や大学生らと協力しながら、子どもたちに自然や水の流れ、生き物のつながりを学んでもらうイベントなどを行っています。

子ども向け濾過実験イベント
琵琶湖に携わり滋賀県で活動することになったきっかけを教えてください。
佐藤もともと大阪出身で、大学時代は四国の川をテーマに開発と環境の対立を巡る社会問題に関する研究をしていました。その後、建設環境系のコンサルタント会社に就職し、全国の川や湖の水質改善のための計画づくりなどを行っていました。そのひとつに琵琶湖があり、水質保全のためのシミュレーションなどを仕事として扱っていました。
建設コンサルタントは全国各地の川や湖に関する仕事ができますが、僕はずっとローカルで仕事をしたいと思っていて、少しフラストレーションを感じていた部分があります。ちょうどその時、滋賀県にいる大学時代の恩師に「よかったらこっちに来ないか?」と声をかけられ、滋賀県へ移住し、今の仕事に就きました。
その頃、琵琶湖の環境を守ろうと、2000年に「マザーレイク21計画」という行政計画が作られ、県内のあちこちで住民や企業、事業者が集まって話し合う場が設けられて活動が行われていました。しかし関わる人の高齢化や活動人口が増えないなど、なかなかうまくいかなかった部分もありましたね。そこでもっと行政、企業、住民がフラットに話し合い、課題解決ができるような場作りをしていこうということになり、2011年に「マザーレイクフォーラム」を立ち上げました。
「マザーレイクフォーラム」では創設以来10年近く、琵琶湖の将来の目標をみんなで作ろうと話し合ってきて、その結果作り上げたのが「マザーレイクゴールズ」です。SDGsは2015年に宣言されましたが、僕らはその前からこのローカルな目標を、時間をかけて作ってきたわけです。活動が功を奏して現在の賛同者数(事業者等を含む)は1,600人ほど、ワークショップは年間約40回開催し、ロゴマークの利用届け出も300ほど。県民の約1/4に認知されています。

魚掴みイベントに参加された子ども達と大学生
琵琶湖の水質や環境保全について官民が連携したそもそものきっかけは?
佐藤1977年に琵琶湖で赤潮が大量に発生し、湖面が真っ赤に染まってしまったことがありました。赤潮の主な原因は我々の生活から出るリンという物質です。そこで、リンを含む合成洗剤をやめてみんなで石けんを使おうという運動が広がりました。主婦が中心となって県内を行脚しながら石けんでも洗濯できるという説明を行い、リンを含む合成洗剤をやめる条例が作られ、その後リンなどを規制する法律にもつながりましたね。このことからも言えるように、滋賀県には、自治と連携で環境をよくしていこうという風土というか、滋賀県的DNAがあると思います。
また赤潮の問題は、私たちが知らず知らずのうちに汚いものを流してしまうと、それが琵琶湖に、まるで私たちの暮らしの鏡のように映し出されるということが如実にわかった事例でもありました。だから美しい琵琶湖が保てるように暮らしの環境もよくしていこうという思いが、滋賀県の人たちに根づいていると思います。
佐藤さんにとっての地域活性を教えてください。
佐藤マザーレイクゴールズが大切にしているのは、創発を生むということ。例えば私たちや行政が考えたことに地域や学生が関わってもらうのではなく、地域の方たちが考えたことや、やりたいなと思ったことに、私たちが持っているネットワークや資源を通じて協力させてもらうということです。「こんなことできないか?」「協力してほしい」という声には極力応えるようにしています。実にいろいろな声が上がってきますよ。例えばモーグルの元オリンピック選手でマザーレイクゴールズの広報大使を務める伊藤みきさんからは、「マザーレイクゴールズの体操を作りたい」といわれました。地球温暖化によって世界中で雪がなくなってきている状況をなんとかしたいという思いから、「体操をして基礎代謝を上げて、エアコンに頼らない体づくりをしようというコンセプトで作りたい」といわれて。最初は私たちも驚きましたが、多くの方のご協力があり、とうとうできちゃいましたね。またアーティストが琵琶湖の漁師とつながって作品を創るとか。マザーレイクゴールズという言葉がきっと何かやりたいなと思っている若い人たちに刺さっているのでしょうね。マザーレイクゴールズをきっかけにいろいろな人達のアイデアが形になっています。また行政や研究者とか、ある意味固い組織の人がマザーレイクを媒介にして地域の人達とつながり、いろんな活動の後押しができるようになっている。それが地方活性化につながっていると感じています。

西浅井で捕った湖魚試食イベント
意見の対立が新たな創発を生む。
その話し合いの場として、
「マザーレイクゴールズ」を活用したい。
佐藤さんにとっての“EVOLUTION✕LOVE”を教えてください。
佐藤私の活動の根源となっているのは、学生時代にしていたダム問題の研究です。環境の重要性を学べる大学に進み、当時の建設省のダム建設計画に対して地域の人たちが「環境破壊だ」と反対をする、環境VS開発の対立を研究していました。その時、建設省の人と話す機会があったのでその時は「そんなんしたらだめでしょ、環境大事にせなあかんでしょ」と文句を言ってやろうと思っていましたね。ところが、「このままだと洪水に対して危ない状況になる。近代的な方法で建設し直さないと地域の人たちの命が危ない」という合理的な説明を聞いて、「この人の言ってはることはほんまや」とものすごく納得して。環境も大切だし洪水リスクを減らすことも大切だし、どっちが正しい、間違っているといっていること自体が問題なんじゃないかと気がつきました。物事を進めようとすると必ず意見の対立がありますが、それはむしろウェルカム。意見の違う人たちがいかに話し合える場を作るかと考えて、今、マザーレイクゴールズを運営しています。SDGsの目標も同じで、こっちのゴールを達成しようとするとこっちのゴールの達成率が下がる、ということがあります。それこそがマザーレイクゴールズの本質であり、このゴールを達成しようとするとこのゴールに影響が出る、さあどうしようかと地域の人々や行政、企業がみんなで話し合うことが大切だと思っています。考えが違う人同士がつながることが何か新しいものを作ったり、突破するエボリューションを生み出します。人々がもっと話し合える場にマザーレイクゴールズを活用していくことが私のEVOLUTION✕LOVEです。
10年後、20年後はどうなっていたいですか?
佐藤今の若い人たちがもっと自由に活動するには、いつまでも僕たちが上で旗を振っていてはいけないと思っています。だから10年後、20年後は引退して、若い人たちの活動を応援する裏方に回りたいなと考えています。

佐藤さんご自身が掲げるびわ湖との約束

佐藤さん、ありがとうございました!それぞれの目的を達成するためにさまざまな人たちの話し合いの場を設け、つなげることを大切にしている佐藤さんの思いと活動を、今後も応援させていただきます。